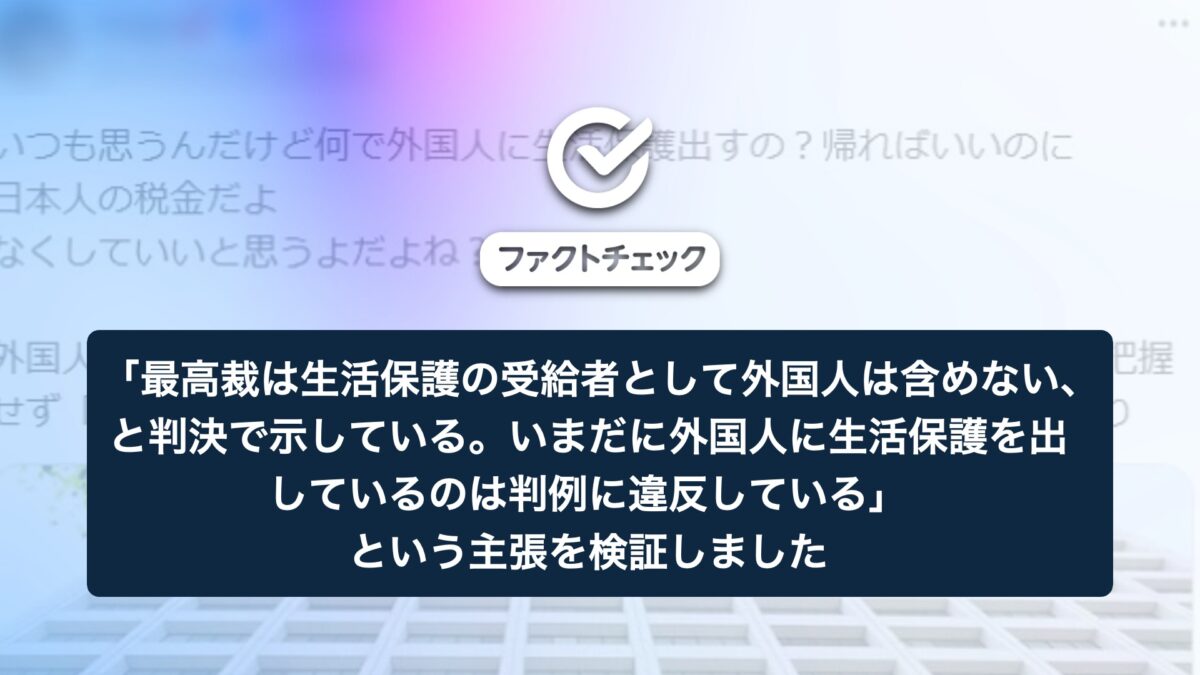「最高裁は、生活保護の受給者として外国人は含めない、と判決で示しています。にもかかわらず、いまだに外国人に生活保護を出しているのは、判例に違反しています。」
検証
2014年の最高裁第2小法廷判決は、「外国人は、行政庁の通達等に基づく行政措置により事実上の保護の対象となり得るにとどまり、生活保護法に基づく保護の対象となるものではなく、同法に基づく受給権を有しないものというべきである。(下線は引用者による)」としています1。つまり、生活保護法に基づく保護の対象ではないと判示していますが、行政措置による保護の準用自体は否定していません。
外国人の生活保護が「準用」になっているのは、日本における戦後の旧植民地政策に背景があります。憲法第25条を根拠とした1950年の新生活保護法では、その対象を「国民」と定めましたが、当時は日本国籍を保有した旧植民地(朝鮮半島・台湾等)出身者がいました。そして、1954年のサンフランシスコ講和条約の締結時に、旧植民地出身者は日本国籍をはく奪されています。しかし、それまで「日本人」として生活保護を受けていた旧植民地出身者の保護を打ち切ることは人道に反するため、厚生省(当時)は通知を発出して、旧植民地出身者も含めたすべての外国人に対し、行政措置として保護を準用する措置を取っています。そして、1981年の難民条約加入を受けて、1986年に国民健康保険法や児童手当法における国籍条項が撤廃されました。ただし生活保護については、「この条約(引用者注:難民の保護に関する条約)において、難民に対する公的扶助は、自国民に与える待遇と同一の待遇を与えることが締約国の責務とされているところでございまして、難民に対する保護の措置、この昭和29年通知により行われることとされて、今日に至っているものでございます。」2として、法改正は行わず、「当分の間」とされた準用をいまでも継続しています。
このような歴史的背景をうけて、外国籍者の生活保護を日本政府は認めてきました。少なくとも、判例上、あるいは政府見解において、生活保護の受給者として外国人を含めないとした解釈は、過去も現在も一切存在していません。
結論
2014年最高裁判決は、生活保護法に基づく保護の対象ではないと判示していますが、行政措置による保護の準用自体は否定していません。外国人への保護は判例違反ではありません。